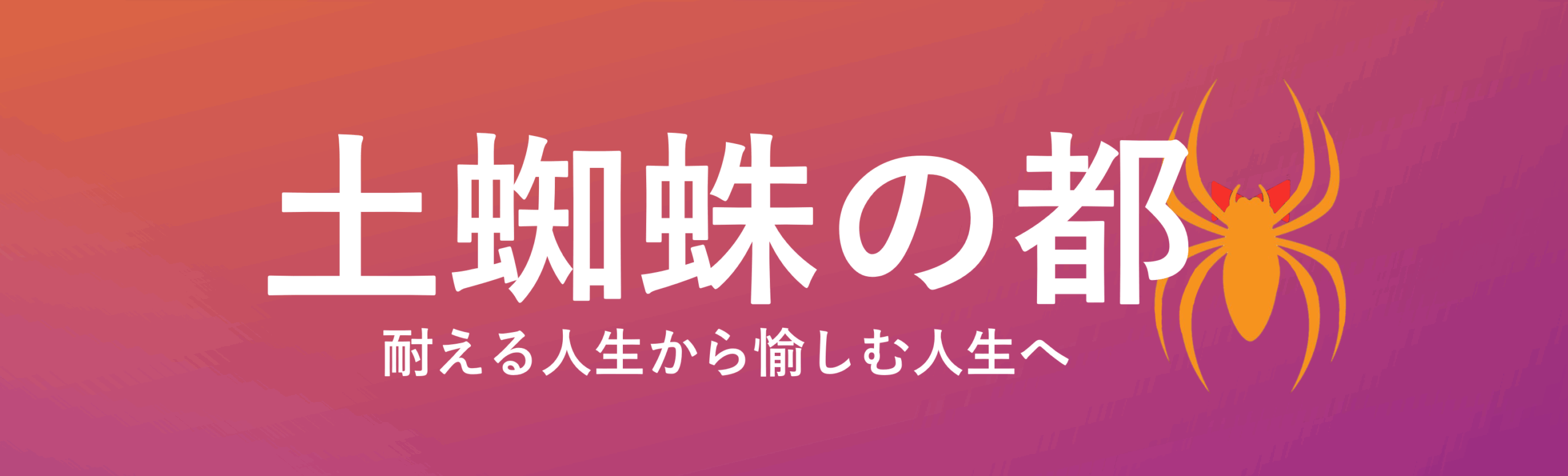ウズグモは私が最も好きなクモのひとつである.
当ブログのキャラクター「土蜘蛛みやこ」のモデルもこのウズグモである.
ウズグモには他のクモにはない特徴があり,本記事ではその面白さを述べる.
①ウズグモの横糸には粘球を使わない
一般的なクモでは,横糸に粘着性のある粘球を使用することで獲物を捕らえる.
一方,ウズグモの横糸には粘球を使用しておらず,別の方法で獲物を捕らえる.
ウズグモには篩板(しばん)という細い糸くずを作る器官があり,この糸くずで獲物を捕らえる.
この糸くずは梳糸(そし)と呼ばれており,ウズグモでは網に大量にくっ付けられる.
網にかかった昆虫は梳糸に体が絡まるか,ファンデルワールス力に引き付けられて捕らえられる.
しかし,梳糸は粘球よりも粘着力が弱く,粘球よりも劣っていると考えられることが多い.
一方,ウズグモの網は雨が降っても絡みつき能力は落ちないメリットがある.
そのため,ウズグモの網は毎日張り替えを行う必要がないと考えられる.
②ウズグモ科には毒がない.
ウズグモ科は鋏角に毒を持たない.
代わりに多量の糸を使って包み込み,包み込みの圧力により獲物に損傷を与える.
その後に獲物を噛まずに,包み込んだ糸の外から消化液をかけて獲物を体外消化する.
近年では,この消化液に毒が含まれている可能性を示唆する研究結果もある.
その研究では,ウズグモの毒の生産が鋏角の毒腺から消化器官にシフトしており,結果として鋏角の毒腺が二次的に失われたことを示唆していた.
③ウズグモ科のオウギグモは扇形の網を張る.
オウギグモは林の薄暗い茂みの場所に扇形の網を張る.
オウギグモは網の要のところで糸を引き,虫が掛かった瞬間に網が緩み虫は網に絡みつかれる.
最近,オウギグモが糸の張力を利用していることが明らかにされた.
オウギグモはクモ本体が網の中心部で網全体を引っ張る形で待機している.
網の近くに獲物が近づくと,その振動を感知したクモはそれまで引っ張っていた網をパッと放す.
すると緊張状態にあった網は緩み,網はまるで矢のようにすごい速度で飛んでいき,獲物を絡めとる.