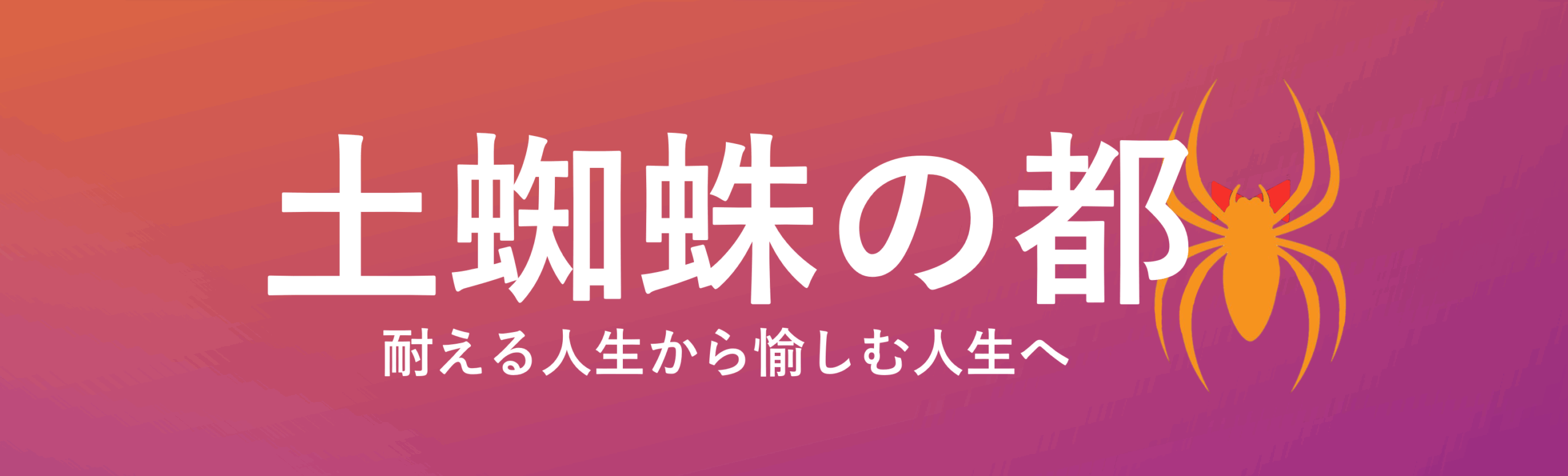トリノフンダマシはコガネグモ科トリノフンダマシ亜科に属するクモである.
本グループは鳥の糞やテントウムシに似ており,捕食者からの攻撃を防ぐ擬態能力を持つ.
しかし,本グループには擬態の他に,張る網にも特徴がみられる.
本記事では,トリノフンダマシの網の特徴について解説する.
①網に使う糸の本数が少ない.
餌を狙う戦略としては,糸の本数に投資するか,糸1本あたりの強さ・粘性に投資するか,の2通りであると考えられる.
ジョロウグモは前者のタイプである.
ジョロウグモは縦糸と横糸密度が非常に高く,飛翔する餌から運動エネルギーを奪う効率が良いため,大型餌に対する餌捕獲能力が高い.
また,密度の高い糸により小型の餌も多く採れる.
つまり,ジョロウグモは糸の本数を高めることで,大型餌と小型餌の両方を捕らえられるようになっている.
但し,目が細かく大きな網であるために全てを張り替えることが大変であり,ジョロウグモでは他に例のない「網の半分だけ張り替える」という方法を採る.
一方,トリノフンダマシは縦糸・横糸の密度が低い水平円網を張るが,横糸の粘性と強度が非常に高い.
横糸の繊維の太さ,粘球の直径が他種よりも遥かに大きいのである.
この糸の特性は,トリノフンダマシがガを専食することと深い関係がある.
ガは鱗粉があるために,クモの網にかかっても鱗粉だけを残して網から脱出することができるため,一般的なクモはガを捕らえることが苦手である.
しかし,トリノフンダマシの横糸の粘球は非常に大きく,粘着性が強いため,この巨大な粘球がガに接着すると,素早くガの体に浸透し,ガは逃げられなくなる.
また,トリノフンダマシの網においては,ガが横糸で捕らえられた瞬間,横糸と縦糸が交差する部分の片側が自然に切れるということも重要である.
この性質によって,捕らえられたガが宙吊りになってしまう.
②トリノフンダマシ亜科の仲間たち
トリノフンダマシ亜科には,①で述べたような円い網を張る仲間だけでなく,三角形の不完全な円網を張ったり,そもそも網を使わなかったりする仲間が存在する.
三角形の不完全な円網を張るのは,ツキジグモである.
三角形の網は3本の縦糸と10本の横糸という少ない本数から作られる.
日本にはワクドツキジグモという種がいる.
網を使わずに獲物を捕らえることができるのは,ナゲナワグモである.
ナゲナワグモでは巨大な粘球のついた1本の糸を振り回して餌のガを捕らえる.
ナゲナワグモもトリノフンダマシと同様にガを専食している.
捕獲した餌がガのオスに偏っていたことから,ナゲナワグモはガのメスのフェロモン様物質を使ってオスを誘引していることが分かった.
更に,オーストラリアにはナワナシナゲナワグモという網どころか糸すら使わず手掴みでガを捕らえるものがいる.こちらもフェロモンを発していると考えられる
③トリノフンダマシ亜科の進化
トリノフンダマシ亜科の進化順を考えるにあたり,フェロモンと網がヒントになると考えられた.
トリノフンダマシの網には,オスだけでなくメスのガも捕まることから,トリノフンダマシはフェロモンを発していないと考えられる.
一方,ナゲナワグモではフェロモンを活用することにより,最小限の糸で獲物を捕らえられるようになった.
このことから,以下の進化順が考えられた.
1)円網を作るクモの一群から,ガに特化した網を作るトリノフンダマシのグループが生じた.
2)捕獲するフェロモンを獲得し,ガを捕まえる効率が大幅に上昇して大きい網を作る必要性がなくなり,ツキジグモなどの不完全な網を作るグループが生じた.
3)フェロモンを獲得することで,投げ縄(糸)だけで獲物を捕るナゲナワグモのグループが生じた.
4)糸すら使用しないナワナシナゲナワグモのグループが生じた.
このシナリオは,フェロモンという武器を手に入れることで,トリノフンダマシ亜科は大きな網を作る必要がなくなったというものである.
しかし,DNAに基づく系統解析を実施した結果,予想外の結果が得られた.
1)系統樹の根元でトリノフンダマシとナゲナワグモが分岐した.
2)トリノフンダマシの仲間から三角網を作るツキジグモが生じた.
3)ナゲナワグモの仲間からナワナシナゲナワグモが生じた.
というシナリオである.
つまり,寧ろ最初にガのフェロモンを使えるグループと使えないグループに分かれ,其々が独自の進化を遂げたというシナリオがDNA系統解析により示されたのである.