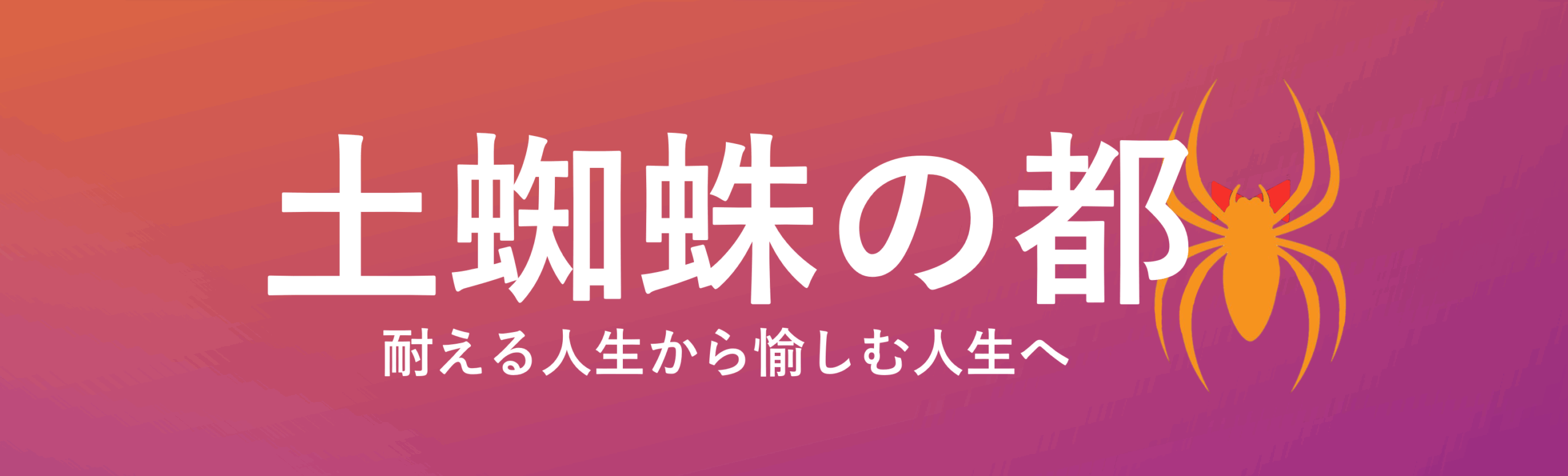節足動物は,鋏角亜門・多足亜門・甲殻亜門・六脚亜門に分けられる.
我らがクモは,この中で鋏角亜門に分けられる.
生物分類技能検定2級動物部門では,この分類に関する問題が頻出される.
自身の備忘録のためにも,私が勉強したことを本記事にまとめておきたい.
①節足動物の付属肢・体の構造について
・節足動物は原則として各体節に1対の付属肢を持つが,複数の体節が合体して合体節を構成したり,付属肢が退化・消失したりしてこの原則に合わないケースが多い.
・鋏角亜門以外の節足動物は頭部に触角(付属肢)を有する.鋏角亜門に触角がないことは,爆発的な多様性を獲得できなかった遠因である可能性がある.
・鋏角亜門以外の節足動物は頭部(第2体節の付属肢)に大顎を有するので,大顎類と呼ばれる.つまり,大顎類は多足亜門・甲殻亜門・六脚亜門から構成される.
・鋏角亜門は付属肢が6対(1鋏角・1触肢・4歩脚)あり,第1体節の付属肢がはさみ状になり(鋏角),体が前体部(頭胸部)と後体部(腹部)の2部に分かれる.更にクモには,頭胸部と腹部の間に細い腹柄があり,そのおかげで腹部を折り曲げることができる.
・上記の4亜門はいずれも現生であり,化石まで範囲を広げると三葉虫なども節足動物に含まれる.(現生は4亜門だけ)
②呼吸器について
・鋏角亜門では,分類群によって異なる
✓カブトガニ,ウミサソリ…書鰓を持つ
✓クモ,サソリ…書肺を持つ.書肺は書鰓に起源を有する(陸上進出にあたり,乾燥しないように体内に収納した)
✓ダニ,カニムシ,ザトウムシ(3馬鹿)…気管を持つ
尚,クモも気管を持つが,2対ある書肺の後対が変化してできたため,3馬鹿とは起源が異なる.
但し,ハラフシグモ類とトタテグモ類は器官を持たず,従来通り書肺は2対あるままである.
※分子による系統関係と呼吸器の種類による系統関係は異なるので注意
・多足亜門は全て陸上性であり,気管と気門で呼吸を行う.
・甲殻亜門…水棲のエビなどは鰓で水中呼吸をする.陸棲のワラジムシなどは白体(偽気管)で呼吸する.
・六脚亜門…気管と気門を持つ.水棲昆虫の幼虫は気門の代わりに気管鰓を持つ.
③複眼について
基本形は中眼(単眼)と側眼(複眼)を備える.しかし,例外も非常に多い.
・鋏角亜門では,分類群によって異なる.
✓ウミグモ⇒中眼(単眼)だけを持つ.
✓カブトガニ,ウミサソリ⇒中眼(単眼)と側眼(複眼)を持つ.
✓その他の鋏角亜門⇒中眼(単眼)と側眼(単眼)を持つ.側眼の複眼は退化してしまった.
・多足亜門
✓ゲジ目(ゲジ)⇒側眼だけを持ち,側眼は複眼である.
✓ゲジ目以外の多足亜門⇒側眼だけを持つが,単眼となっている.
・甲殻亜門と六脚亜門は基本形通りである.
④下位分類について
[鋏角亜門]
✓クモ綱…クモ目,コヨリムシ目,ザトウムシ目,クツコムシ目,ヒヨケムシ目,カニムシ目,サソリ目,ウデムシ目,ヤイトムシ目,ダニ類
[多足亜門]
✓ムカデ綱…ゲジ目,イシムカデ目,オオムカデ目(トビズムカデ),ジムカデ目(ツメジムカデ)
✓ヤスデ綱…オビヤスデ目(ヤケヤスデ),タマヤスデ目(ヤマトタマヤスデ)
✓コムカデ綱…コムカデ
✓エダヒゲムシ綱…ヤスデモドキ
[甲殻亜門]
・貧甲殻上綱
✓貝形虫綱…ウミホタル,カイミジンコ
・多甲殻上綱
✓六幼生綱…カイアシ
✓鞘甲綱…フジツボ
✓軟甲綱…口脚目(シャコ),等脚目(ワラジムシ,ダンゴムシ,フナムシ,オオグソクムシ,ヨコエビ,ワレカラ),オキアミ目(オキアミ),十脚目(クルマエビ,ヨコエビ,テナガエビ,イセエビ,ザリガニ,ヤドカリ,タラバガニ,カニ)
※ワラジムシ,ダンゴムシ,フナムシは同じワラジムシ亜目に属する.
※タラバガニはヤドカリと近縁
・異エビ上綱(六脚亜門はここに含まれる)
✓鰓脚綱…ホウネンエビ,カブトエビ,ミジンコ,ゾウミジンコ
✓ムカデエビ綱…ムカデエビ