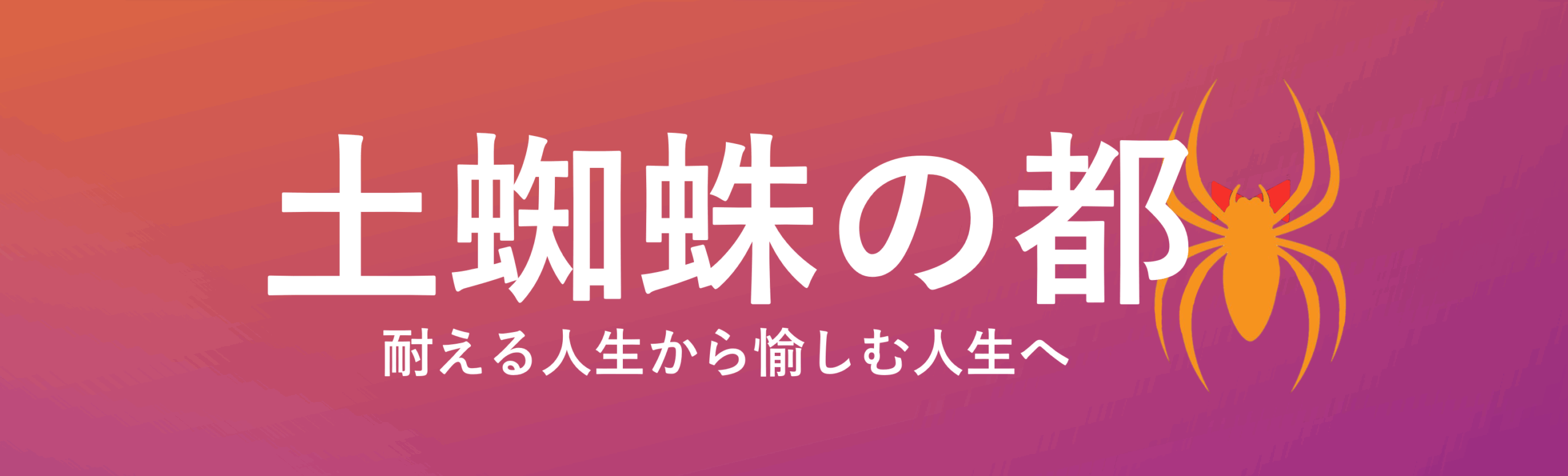クモの多くは熱帯に起源を持つが,熱帯から温帯に分布域を拡大し始めた最,温帯における冬の存在は定着にあたって大きな障壁となったことと考えられる.
クモは様々な戦略を進化させることにより,冬の寒さを克服してきた.
①体が凍らないための戦略(凍結耐性)
寒さによって生物が死ぬ要因として,体が凍ってしまうことが挙げられる.
クモは体が凍らないようにするために,体組織の凍結開始温度(SCP)を調節する能力を獲得した.
SCPは生物分類群の間での差は小さいが,越冬する場所による違いが観察されている.
例えば,地中やリター層など直接冷たい外気に曝されない種のSCPは高く,草本や樹木の枝など冷たい外気に曝される種ではSCPが低く,体が凍り辛くなっている.
また,SCPは同じ個体であっても季節によって異なる.
例えば,札幌のオオヒメグモは夏の-7℃から冬の-20℃まで13℃ほどSCPを低下させられる.
このことが冬を凍らずに生き延びる上で重要である.
クモが冬に自身のSCPを下げられる理由は,冬に摂食をやめるためであると考えられている.
体が凍ると言っても実際に凍るのは体液であり,水が凍るメカニズムを考えれば理解しやすい.
水が凍るためには「氷晶核」が必要であり,なにも混ざっていない綺麗な水は中々凍らない.
つまり,ある程度水の中が汚れ,氷晶核になり得る粒子が存在しなければならない.
そして,クモの体内においては消化管の内容物が氷晶核になっている可能性が考えられた.
このことをオオヒメグモで実証した実験があり,クモを絶食させるとSCPは低下するが摂食を再開すると直ちにSCPが上昇することが示された.
但し,摂食行動が抑制されるのは,冬からではなくてもう少し早い秋からであると考えられている.
短日条件(秋の到来を示唆する日長の短い条件)においてクモを飼育すると,たとえ気温が20℃であっても摂食をやめるようになる,という実験がある.
このように,短日条件になるとクモは冬になるよりもずっと早めに耐寒の準備を始める.
これは光周期による遺伝的なメカニズムであると考えられる.
②長期的な寒さを凌ぐための戦略(冷温耐性)
越冬中のクモにとっては凍結だけが低温死の原因ではない.
凍結しない温度ではあっても,一定の低温に長時間曝されると死んでしまう.
このような死に方を冷温障害と良い,凍結よりも冷温障害の方が冬の死亡要因として重要と主張する学者も多い.
冷温障害を測定する上で,「一定時間クモをある低温に曝した際に,50%が生き残る温度」である50%冷温致死温度が使用される.
SCPと同様,50%冷温致死温度(冷温耐性)を季節によって変化させることによって,長期的な寒さをクモは凌いでいると考えられている.