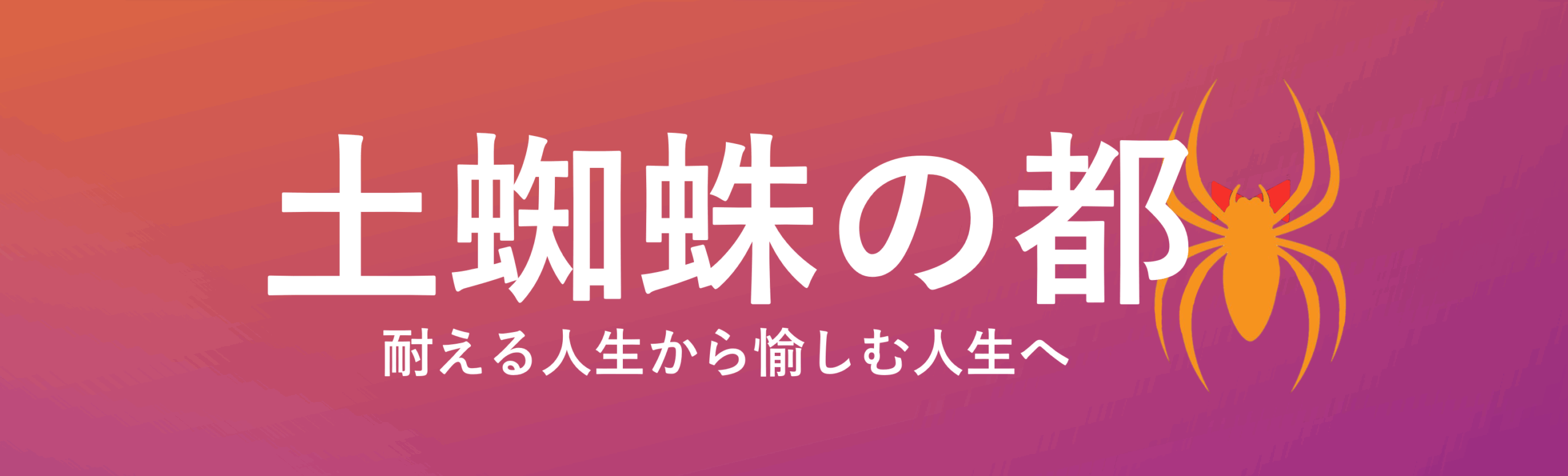この記事は「クモと生殖戦略(オス編③)」の続きである.
前回記事の通り,メスに共食いされてしまうリスクを背負いながらオスは交接を仕掛ける.
しかし,逆に共食いされることを受け入れるオスもいるという.
本記事では,オスが共食いされることの意義について紹介する.
沢山食べて卵を多く作ることがメスの成功に繋がるから,メスは食べられる物はなんでも食う.
栄養バランス的には同種のクモは自分と似た栄養成分から成るため,食物として無駄がない.
実際に,共食いしたメスの産む子は生存率が高くなることがニワオニグモなどで実証されている.
そのような中でも異質であるのが,セアカゴケグモである.
セアカゴケグモのオスは交接中に自らの体を主体的にメスの口の前に投げ出すのだ.
セアカゴケグモのオスはメスよりもあまりにも小さい(体重でメスの1-2%程度)ため,食われることによって産卵数を増やすというメリットがなさそうに考えられた.
どうやら,セアカゴケグモのオスが自ら共食いされに行く理由には,交接時間がありそうである.
メスに共食いされた時の方が交接時間が2倍以上伸び,受精率が上がったという報告がある.
つまり,メスがオス自らの体を食べている隙に,オスは交接を仕掛けているのである.
加えて,交接したオスを食べたメスは,その多くがその後から来た別のオスとの交接を拒否するようになったとのこと.
やはり,身を削って行う求愛行動はメスにとって信頼できるのであろう.
しかし,『クモのイト』を記した中田先生の言葉を引用すれば,
「私の本能が,この行動が合理的だと認めることを拒絶しろ!と叫んでいるのですが,自ら身を捧げたオスが自分の子を沢山産んで貰っているという証拠を見せられては,認めない訳にはいきません.合理的,という言葉がトラウマになりそうです」とのこと.
男なら誰しもこのように思うだろう….