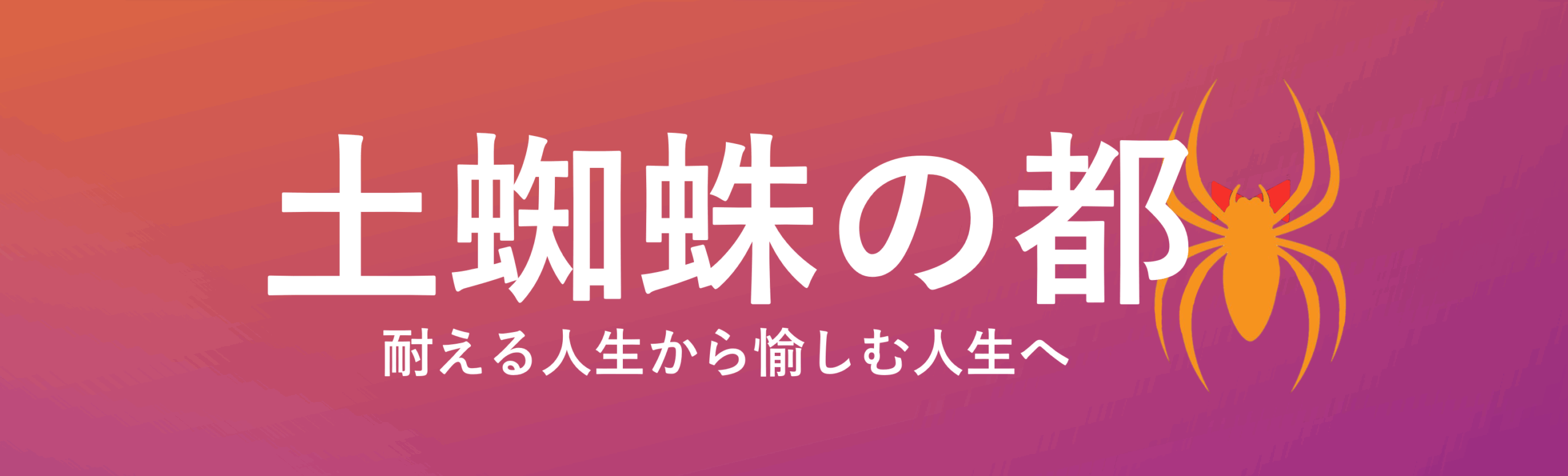造網性のクモについて,多くの場合はメスがオスよりも体が大きい.
特にジョロウグモでは,オスのサイズを人間と考えた場合,メスは象くらいのサイズになる.
なぜ,このようにオスとメスの間で体の大きさに明瞭な差が生じたのであろうか.
研究者たちの考えた説を本記事では紹介していく.
①メスが大きくなった説
この説では,元々オスとメスは同じサイズであったが,世代を経てメスが大きくなる方向に進化したと考えられている.
メスが大きくなった理由としては,卵を多く抱え,多く産むことができるようにするためと考えられる.
一方,オスについては,幼体時点で死んでしまったり,メスの網を探している間に殺されたりすることが多く,体の大きさが重要な成体オス同士の喧嘩にまで辿り着ける個体がそもそも少ない.
だから,オス同士の喧嘩も多くは発生せず,体の大きさが重要なシチュエーションがあまりない.
また,『クモと生殖戦略(オス編①)』で述べたように,オスは(たとえ体が小さくとも)早く最終脱皮を終えるほど,より早く処女を待ち伏せできるようになる.
よって,オスには体を大きくすることについてメリットとデメリットの両方があり,自然選択の過程で強くは形質が残らなかったと考えられる.
②オスが小さくなった説
近年では,「小さなオスは俊敏に動けるために,メスと交尾する上で有利」と考える重力仮説が提唱されている.
交接しながら食われるとか,交接した後に食われるとかであればまだオスにとって食われるメリットがあるが,交接前に食われることも多くデメリットの方が大きい.
メスは高い位置に網を張っているので,オスはメスと交接する際に重力に逆らって高い位置に移動しながら,メスの攻撃をかわさねばならない.
だから,オスはメスからの攻撃をかわすため,俊敏に動ける小さな体に進化したのではないか,とこの説では考えている.
実際,クモの歩行速度などの計測データから,理論上最も素早く動ける体のサイズを算出した結果,その予想された最適な体の大きさと実際のオスの体の大きさがよく一致したとのことである.
しかし,オスとメスの体の大きさの関係はグループ間でも違いが大きく,一元的な個体はなさそうにも思える.