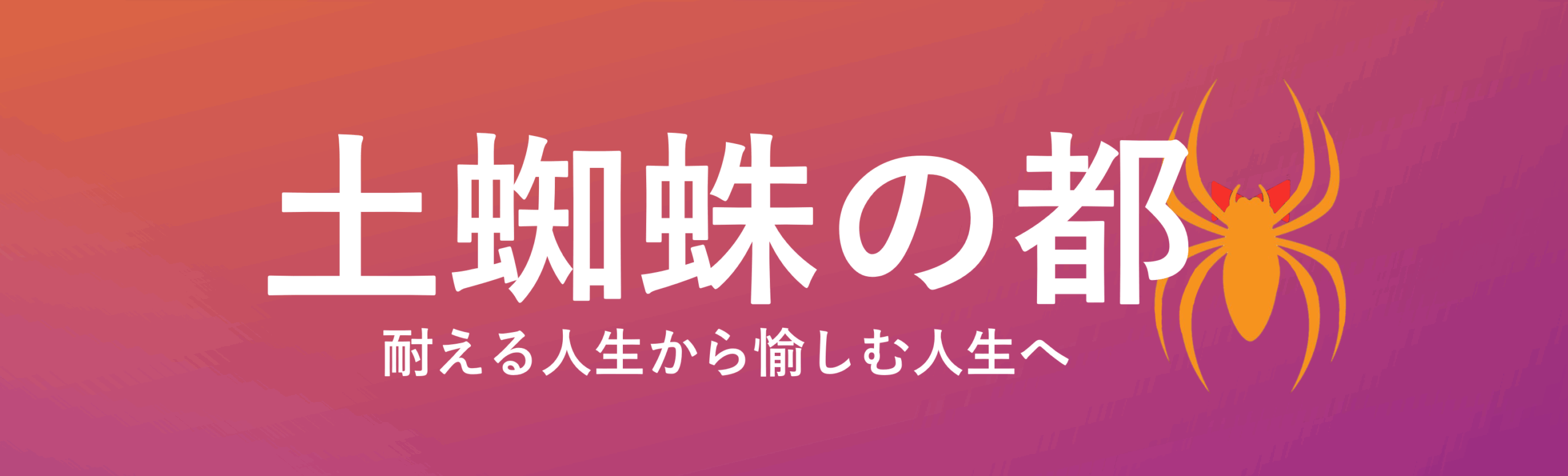カマツカは河川の底を這って泳ぐ淡水魚である.
河川の砂を網で掘ると,偶然に採れることもある.
元々カマツカ属は1種であったが,近年の研究で3種に分かれることが判明した.
山梨県には2種のカマツカ属魚類が棲息するため,本記事ではその紹介をする.
①日本に棲息するカマツカ属
カマツカ属の遺伝構造を調査した研究に,富永氏の『Cryptic divergence and phylogeography of the pike gudgeon Pseudogobio esocinus (Teleostei: Cyprinidae): a comprehensive case of freshwater phylogeography in Japan』がある.
この研究では本州以南に棲息するカマツカ属を網羅的に採集し,その遺伝構造を決定した.
その結果,日本アルプス以東に棲息するスナゴカマツカ,日本アルプス以西に棲息するカマツカ・ナガレカマツカに分かれることがわかった.
カマツカ・ナガレカマツカは分布域が重なっていることが分かっており,このことについて同研究では分岐年代推定の結果から以下のように考察されている.
(1) 中新世後期にはナガレカマツカとスナゴカマツカの共通祖先が日本に棲息していた
(2) 前期鮮新世に日本アルプスが形成され,ナガレカマツカとスナゴカマツカが分岐した.その後でカマツカが大陸から日本に入り込んだ
(3) 前期更新世にカマツカは西日本から東日本に進出しようとするが,日本アルプスに阻まれて,カマツカは日本アルプス以西に棲息するようになった.
②山梨県に棲息するカマツカ属
同研究では山梨県に棲息するカマツカ属はスナゴカマツカだけとされているが,私の調査によると山梨県にはカマツカとスナゴカマツカの2種が棲息しているようである.
カマツカとスナゴカマツカは一見違いが判別し辛いが,スナゴカマツカは唇が暑く,口髭が長いという特徴が観察される.
また,カマツカは緩やかな河川を好む傾向がある一方,スナゴカマツカは急流に棲息していた.
実際,私は釜無川でスナゴカマツカを採集したが,命の危険を感じるような急流の砂の中に棲息していた.
また,どうやらカマツカとスナゴカマツカは交雑が可能なようである.
私が山梨県で採集したカマツカ属の遺伝子を決定した結果,ミトコンドリアDNAはカマツカだが,核DNAはスナゴカマツカということがあった.
果たして山梨県のカマツカ(種)は移植なのか,在来なのか….