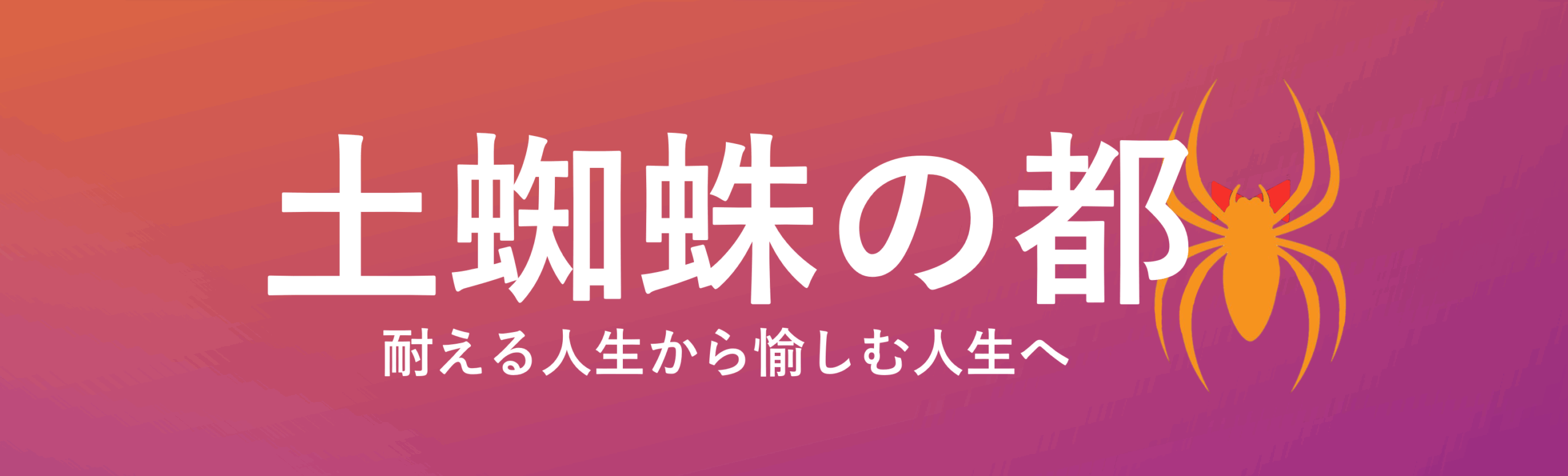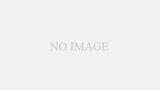こんにちは,「土蜘蛛の都」プロジェクトを企画しました白汐黎(はくせきれい)と申します.
私はアトピー,虐待,ヤングケアラー等の辛いことに囲まれ,これまで人生を耐えるものとばかり思っていました.
しかし,私は研究活動等を通じて思考が馴化され,今では人生を愉しむものと思えるほどにまで成長しました.
ここでは,私,白汐黎の「耐える人生」を「愉しむ人生」に変えてくれた考え方を一挙公開したいと思います.
〇はじめに:思考体系を構築することの重要性
以下で紹介する考え方は,全てひっくるめて「己の幸せ理論」と呼んでいます.
「己の幸せ理論」では,他人の評価に依存せずに己の幸せを維持できるようになることを目指しています.
これは考え方を体系化した思考体系の一種であり,心の中の法律とも言えます.
私は自らに適合した思考体系を構築することこそ幸せへの近道と考えています.
思考体系を構築することで,落込んでしまった時も一貫性のある軸に立ち返って考えることができるため,ブレない精神を育むことができると考えられます.
以下の己の幸せ理論は,あくまで私に適合した思考体系でありますので,必ずしも万人に適合するとは限りません.寧ろ,万人受けはしない考え方なのかな,とすら思っています(そのため,「嫌われ者のフィロソフィ」という蔑称も付けています).
しかし,重要なのは己の幸せ理論の内容自体ではなく,あなた自身に適合したオリジナル思考体系を築くことであり,あくまで以下の己の幸せ理論はオリジナル思考体系を構築する上での参考にしか過ぎません.
また,以下には一見綺麗事に見えることばかり記載されていますが,私自身も初めからこの考え方ができたわけではありません.この考え方が正しいと意識的に思い込み,数カ月して漸く使いこなせるようになりました.
「こんなやつにできたのだから,俺にできない筈がない」というばかりに,意識的に思い込むことを継続していただけるとよろしいかと思います.
以下,自身のワードからコピペをしているため,文章が見づらいかもしれませんが,ご容赦ください.
〇座右の銘:人生の本質は「己の幸せ」「愉しむこと」
・人は皆平等ではない.多くは生立ち(遺伝子・環境等…)で決まっている.これは否定できない事実として受け入れなければならない.なぜなら,我々は「自然淘汰」の岐路に立たされた一生命に過ぎないから.自然淘汰は,変異というトライアンドエラーを繰り返しながら,より現在の環境に適応した生物を選別する作業と言える.即ち,人間には自然界に適応し,子孫を残す者と適応できずに子孫を残せない者が存在することは自然界の理から当然であると言える.これは認めざるを得ない事実であり,受け入れなければならない.しかし,だからと言って落ち込んではいられない.我々弱者はこの自然淘汰に抗わなければ,幸せで在ることはできない(幸せになるでなく幸せで在ると記載するのは,いかなる状況下でも今が幸せと思うから).
・人生の本質は己の幸せ.私にとっての幸せは己が愉しむことである.よって,「己の幸せ」=愉しむこと.「今あるものを愉しみ, より良い未来を目指すこと」だから今の自分がどうだからといって気にする必要は無い.理想とする己を本気で想像し,それに向けて努力していれば良い.今と未来,どちらを愉しむか?という問いはよくあるが, 答えは両方.過程と結果を愉しむのだ.これはエネルゲイアと呼ばれる.結果だけを愉しもうとするのはキーネーシスと呼ばれ, キーネーシスだけでは永遠に満たされない.完璧でない今すら愉しむのだ.矛盾するようだが,完璧でない己を受け入れ,完璧であると思い込み,より完璧を目指して行動するのだ.
・己の幸せは常に「今を最高と思い,愉しむこと」(エネルゲイア)によるものである.それゆえに,ないものを見るのではなく,今あるものを愉しむように意識しなければならない.物事を悪く捉えず,良く捉えるよう心掛けなければならない.逆に己の幸せを脅かす事象にはあまり関与せず(SNS,ネット掲示板が好例),そのことについて深く考えてはならない.
・しかし,今が愉しいだけでは足りない.「今のままで未来も愉しめるか?」という風に考えることも必要(キーネーシス).やりたいことそ全て諦めず,挑戦し,今も未来も愉しんでこそ,己の幸せと言える.
・人生は思い込みで決まっている.よって,己が幸せで居続けられるような思考体系を構築し,それが正しいと思い込み,行動することが大切.「思い込み」とは今の不幸を幸せと無理矢理思い込むという意味ではない.「思い込み」とは不幸ではなく今ある幸せに目を向けることで今を幸せと感じることを言う.ないものではなくあるものに目を向けて幸せを感じるということ.もしくは悪いことを都合よく解釈する:悪い事の裏に転がっている良いことに目を向ける.
・成功することは難しいが,幸せになることは簡単.そして,有難いことに人生の本質は,成功ではなく,「己の幸せ」.例え成功しても,従来の考え方のままでは永遠に幸せになれない.しかし,考え方を変えれば今すぐにでも幸せになれる.それは,自分が幸せだと思い込むこと.人生は思い込みでできている.そう思ったらそう,そうじゃないと思ったらそうじゃない.人生は思い込みでできている.最高の人生にするのも,最悪の人生にするのも自分の思い込み次第.
・己の幸せを傷つける因子を見ないようにする.SNSやネット掲示板.これらを遮蔽するだけでも己の幸福度は容易に上昇する.
〇目的論と原因論(アドラー心理学),パワハラ関連(自分本位主義)
・「目的論」とは思い込んだ通りに人生がなる原則.これは思い込んだ通りの行動をするようになるから当たり前.己のリミッターとなるのは常に己の精神.できないと決めつけるのは常に己自身.己の理想とする己を常に思い込み,行動をし続けよ.
※「目的論」とは自らの心の中にある目的によって結果が生じるという考え方であり,これの対義は「原因論」である.例えば,原因論では「アトピーが原因で大学受験に失敗した」と考えるが,目的論では「アトピーを言い訳にしたいという気持ち(目的)から大学受験に失敗した」という考え方である.目的論はストイックな考え方なので万人受けしない.
・情緒は「自己」と「自我」によって決まる.「落ち込む前に行動する」という考え方の障壁となる「自我」.「自己」は,「こう在るべき」と思い,己をプラス方向に律しようとする理性的な自分を指す.「自我」は,自己に反し,己をマイナス方向に持って行こうとする自分を指す.鬱はこの「自我」が巨大化して「自己」を押しつぶしている状態.つまり,「落ち込んでいても仕方ない」と理性的な「自己」はわかっていても落ち込んでしまうのは「自我」の所為である.
※自分なりに考えた「自我」が存在する理由…自分(=自己+自我)は変わりたいと思う.しかし,「変わる」ことには失敗するリスクが伴う為,リスクを避けようと「自我」が働く.目的論的には,この「自我」が強く働くことで「変わらない」という目的に向かっていく.逆に,「自我」の存在に気付き,常に「自己」が「自我」に負けない状態を保持することで,「変わる」という目的に向かって進む.「自我」に打ち勝ち,「自己」をコントロールしてこそ目的論を扱えるようになる.
・目的論は上司に理不尽に怒られた際,平静を保つのに使える.「私が原因で係長は怒っているのではない,係長は怒りたいから怒っているのだ(=自我による欲求に支配されている)」「無能なのは新人をうまく扱えずにトイレでサボる係長自身だ.他人の所為にばかりするんじゃねぇ」という具合に.私が職場でパワハラを受けた際にはこの考え方で1年間乗り切っていた.自分が気持ち良くなることを優先して他人を傷つけることは許されない.本当にその行為はその人のことを想ってしているのか?自分が気持ち良くなるためではないか?このことを常に考えて一つひとつの行動をすべきである.
・パワハラ関連で…,例え嘘だとしても,「(叱責・他人の評価が)効かない」「(噂に)興味ない」と思い込む.実際,じわじわダメージは受けているが,これらを真に受けて歩みを止めるよりマシ.
・パワハラ関連で…,他人に壊されるくらいなら他人を壊すべきである.また,他人に壊されるくらいなら,情報遮蔽を行うことも辞さない.
※「他人を壊す」とは,暴力・暴言によってではない.相手になにをされても耐え抜き,「こいつにはなにをしても効かない」と思わせて諦めさせることを指す.
〇無価値の世界と好都合解釈(つくよみちゃん様の考え方を私流に改変)
・物事は元来無価値である.世界は元来無価値というのは,価値観が存在しないという意味ではなくて,「絶対的な(万人共通の)価値は存在しない」という意味であり,物事に対して価値を付加するのは人間である.だから,価値とは人間が構築した定義に過ぎず,通念に過ぎない.それゆえ,社会通念に囚われずに自らが幸せを保てる方向に都合よく解釈するべし.結局は己の位置づけ次第.己の幸せ理論上,都合よく解釈して己の幸せを保つことは大切.しかし,それにより他者に迷惑をかけてはならない.それは酒や異性に泥酔して他に迷惑をかけることと同じだ.例外は,逆に他に自らの幸せを破壊されそうな時.自らが破壊される位なら他を破壊して己の幸せを保て.
・物事に価値を付加するのが人間であり,自分自身で価値づけして良いと考えると,人生に無駄なことはないと考えられる.
・大きな挫折をした直後は膨大なエネルギーが発生しやすい.このエネルギーを利用すれば壁も乗り越えることができやすい.だから,ただ落ち込んでなにもしないのは勿体ない.但し,落ち込むのではなく,悩むのは良いと思う(悩むとは,前に進もうとする策を考えること).だから,挫折はさぁ,ご褒美なんだよっ!
・挫折は人生で一番大切な考える時間である.ここで落ち込んでいては勿体ない.だからこそ「色々あったけど,それらがあった御蔭で今の己がある」精神.「人生は自分の意味付け次第.そう思ったらそう.それゆえ人生は既に全て決まっている」.私は沢山挫折と遠回りをしたが,結果的に私が一番やりたい研究の道に戻る兆しが見えた.人生に無駄なことなど一つもなく,全ては己の意味付け次第.私は挫折をする度に新しいアイデアが生まれた.
・考えても仕方のないことは考えない.己の幸せを傷つけるくらいならそんなこと考えない方が良い.
・参考として考えたこと:「人の役に立つ行為」,「社会に還元される研究」は価値がある?
勿論,役に立てれば,された側にとっては価値があると言えよう.しかし,行為の主体となるあなた自身はどうだろうか.前提として,「人の役に立とうとする前に,自分の役に立てよ.自分も満たせないような人間に他人を満たせる筈がない」と思う.なので,行為の主体にとっては,それをすることにより幸せを感じられるのであれば価値があると言える.逆に,社会に言われるがままに,「人の役に立つ」ことは良いことという通念に従い,嫌々やることには価値がないと考えられる.自分と他人の両方にとって役に立つ自分を目指すべきである.
これは研究にも言えることである.研究は社会に還元される必要があるため,意義を持って研究に取り組まねばならない.しかし,自らが愉しさを感じられない研究は継続することが精神的に困難であり,得られる成果もそれなりになってしまう.自らが愉しみつつ,社会に還元できることが研究者としての理想であると考えられる.
〇住めば都,暗い社会の明るい網
・いくら手に入れても健全なマインドがなければ満たされない.逆に健全なマインドさえあればなにもなくとも,あるものを見て満たされることができる.金持ちになっても彼氏・彼女ができても常になにかしら満たされない部分はある.それを見て嘆いている限りは永遠に苦しいまま.逆に今ある幸せを享受できれば誰でも今すぐに幸せになれる.幸せになれれば生きる理由を考えなくなる.
・他人と比べると見落としがちだが,実は身の周りには幸せは沢山転がっている.小さな幸せをかき集めよう(『最近嫌な事続いてるからお前らの小さな幸せ書いてけ』より).
・全ての事象には意味がある.悪いことの裏には沢山良いことも転がっている(2chのアトピー板より).その事象に対する意味付け次第で幸せにも不幸にもなれる.嫌なことがあっても前向きに捉えようと意識することで幸せになれる.
・隣の芝生が青いのはなぜか?他人の良い所と自分の悪い所を比較しているから.即ち,比べ方が対等でないから.逆にこちらの良い所を引き合いに出せば,隣の芝生なんてゴミになる.他人と比べることは己の幸せにおいて最も無駄な行為.
〇矛盾世界論
・一見矛盾するが,自己を前に向かせるために必要な考え方を「矛盾世界論」という.矛盾しているように見えるが,寧ろ考え方として矛盾している方が精神的に安定する場合が割とある.一見矛盾するように見えるが,それが最適な状態であるという理論が矛盾世界論である.以下では例を紹介する.
・例:「自尊他尊バランス」
自分は1つのことに特化するのに長けており,この能力はこの上なく素晴らしいものと考える.しかし,職場にいる人達のバランスに長けている能力も尊敬している.異なる能力を持つ者たちがお互いを認め合い,苦手を補い合ってこそこの世界は成り立つ.
・例:「自然淘汰への反逆」
私は大抵のことは生立ちで決まると考えている.しかし,自分の人生は自分のものであり,自分自身で責任を取らねばならない.だからこそ,自分の力でこの自然淘汰という宿命に抗わねばならない
・例:「尊敬はしているけど,嫌いだよ」
確かに凄いとは思うけど,人間として好きかどうかはまた別問題である.私は職場で上司に媚び諂う人間が嫌いだ.しかし,彼の生き方はある意味正しいと思うし,純粋に凄いとは思う.私は私で正しいし,彼は彼で正しいと思う.だから,彼の生き様を否定しない.だが,嫌い.
・例:「エネルゲイアとキーネーシスの共存」
今の時点で完璧であり,今の己を受け入れる.しかし,矛盾するようであるが今の己は完璧でない.極めれば極める程に物事は愉しくなるから,未来をもっと愉しむために更なる努力する.
〇あいまい世界論,0.5の思考
・白黒つけるよりもあいまいな世界を認めた方がなぜか納得が行くことが多く,この現象を「あいまい世界論」と言う.1と0の中間として「0.5の思考」とも呼ぶ.
・「どっちでも良い」という感情を使いこなそう.この世界は神が創り,定義(価値)は人間が作ったものであるために,元来無価値である.だから,己の幸せを保つためであれば,1として考えても0として考えてもどうでも良い.だから,己の幸せを保つために0.5(即ち,どっちでも良い)という風に考えても問題ない.どっちでも良いという感情は,興味がないことと興味があることの中間なので,相手を尊重しつつもそれに傾倒せずに済む.
・「1の思考」は思想を強くしすぎる.だから,0.5の思考を推奨する.「1の思考」だと,その思考以外の人間を軽く見るようになってしまう.また,「1の思考」だと,その道が潰えた時に大ダメージを負いがち.特に日本では0.5の思考の者が多く,1は弾かれやすい.どうしても譲れない矜持的な部分は「1」でも良いが,どうでもいい部分に関しては0.5を心掛けよう.
〇一つひとつの言葉の重要性
・一つひとつの言葉に気を配る.例えば,「成功」という言葉は他人と比較する意味が入るのであまり好きな言葉ではない.そこで,私は「やりたいことを通す」と呼ぶようにしている.こういう微妙にニュアンスの異なる言葉の使い方に気を配ることで思考が洗練されていく.
・ポジティブ思考という言い方は嫌々やらされている感があって嫌.こういう思考を意識的に行うのであれば,中二病的なかっこいい名前をつけてモチベを上げるべき.「嫌われ者のフィロソフィ」や「矛盾世界論」もその類.
・プライドには2種類ある.矜持と見栄.矜持はなくてはならず,見栄は捨てるべき.己の極めたいことに対して矜持を持ち続け,それを愉しむ.私にとって人生の終焉とは,矜持と愉しさを追求しなくなり,見栄で仕事をするようになることであると思う. そうなってしまえば,私の大嫌いな人間と同じである.
・承認欲求や金やモテが目的でも良いが,メイン目的に据えない.承認欲求や金持ちになりたい,モテたいという思考自体は否定しない.しかし,それ自体を主目的とすると他人に合わせたり他人と比べたりして人生本来の本質を見失う.というか,上記の欲は際限がなく,完全に満たすことは永遠にできない.人生の本質は常に「己の幸せ」であり,愉しむこと.己の幸せであれば,自らの解釈により幸せを感じ,今すぐに自身を満たすことができる.
〇よだかの法則,分業社会
・あらゆる悩みは,取り組んでいる物事に対して全力を尽くさないことに起因する.この法則を『よだかのほし』に習い,「よだかの法則」と呼ぶ.トップになること自体は重要でないが,トップになるための努力をしないことは悩み落込む原因となる.
・蛋白質やクモと同じで,人のコミュニティも個性の多様性によって成立している.即ち,私にしかできない使命があって,それを愉しめば良い.但し,そのことに関してはトップを目指して努力する.自己の極める範囲外のことについては他人に負けていてもどうでも良いが,自分の極めようとしていることについては(負けることは仕方ないにしても)初めからトップを目指さずに妥協することは落込む原因となる.一方,1個だけを極めるとなると,それに関してすら他人に全く勝てない場合,精神的に来てしまう.なので,極める対象は複数あることが望ましい(例えば私の場合,クモだけでなく淡水魚,日本史,美容,哲学等にも関心がある).
・先程から散々他人と比べるな,と言ってきたが,ここまで日本で長い間生きてきた以上は完全に比べないで生きることは不可能である.よって,己の中の「よだかの星」となる部分に関しては他人に絶対負けない気持ちを持つことで精神的に安定すると考えられる.
・人1人にできることは限られている.できないことはできないと認め,受け入れなければならない.この世界は全員が等しくはなく,各々できることできないことがある.蛋白質やクモのように互いに分業していけば良い.その分,自分にできることは,よだかの星のように誰よりも強くあるべし.
〇他者不理解の原則
・人は決して他人を理解できない.なぜなら,その人は当人ではないから.他人を理解したつもりで居ても実際のところは1%も理解できていない,単なる傲慢に過ぎないのだ.だからこそ,他人に努力を強要することはできず,当人のモチベーションを引き出すことしか他者にはできない.よって,他人の考えを理解することはできないが,(他人に迷惑をかけない範囲内で)全て受け入れるべきものである.他人の価値観を否定せず,尊重するよう努める.
・こちらの興味を理解して貰うには相手の興味を切り口に即して伝える必要がある.ポスターを貼ろうが,通知を送ろうが興味のない人は興味を持ってくれない.だから,相手の興味分野を切り口にして自らの興味分野を伝える取組が必要である.
〇八百万の神則
・世界の存在理由に目的はなく,全てが元来無価値である.価値とは人間の脳が物事に対して行う意味付けにより見出されるものに過ぎない.これが己が神である根拠.私も神であり,あなたも神である.自身の神は常に己自身である.私という神が統治する脳内の世界においては,価値を「愉しむこと」としている.
・私も神,あなたも神,みんな神.これは日本の八百万の神の考え方に近いかもしれない.但し,神である効果が発生するのは自己の属する範囲(つまり,脳内)に限り,他人に対しては有効でない.全知全能の神を崇めて今の己とは関係のない天国を目指すようなキーネーシスな宗教よりも,互いを神として尊敬し合う神道の考え方が好きである.
※白汐黎は幼少期に父親にキリスト教の教会に通うことを強制されていたため,基本的に宗教嫌い.
〇家族に対して
・親ガチャは確実に存在する.だからと言って,親に八つ当たりをすることは最低(親も望んでそう産まれたわけではない).それゆえ,自分が自分であることの責任は誰にも帰属せず(強いて言うなら運命の所為),他人と比べることに意味はないので,落ち込む前に行動し続けることが大切.どうしても変えられない部分もあるが,行動で変えられる部分も多い.自然淘汰(親ガチャ)に抗え.
・親に感謝する.己の境遇に感謝する.他に感謝する.表面だけでなく心から感謝する.感謝できない事象にも感謝する(心は表出する).家族や他人に八つ当たりすることは最低なことと刷り込む.家族に八つ当たりしないだけで私の父親とは差別化ができる.
・参考として考えたこと:私を虐待してきた父親を受け入れることについて
虐待は到底許される行為ではない.しかし,私の父親も祖母から虐待を受け,弟と比較され,その経緯も理解できる.確かに虐待を受けていた幼少期は父を受け入れることはできなかった.しかし,亡くなってからは受け入れるように意識している.実際,父親にはここまで育ててくれた恩義を感じているし,(ヒステリを起こしていない時の)父のことが好きでもある.加えて,祖母のことも受け入れる.祖母の経緯は知る由もないが,きっとなにかしらの苦労をしてきたのであろう.結局,特定の誰かが悪ではないのだ.ただ運が悪かっただけに過ぎない.そのように弁えるようにしている.受け入れることとは許すことではない.ただ,理解をしようと努め,自らがその行いをしないよう律することである.
〇仕事について(個人事業主)
・就職してわかった.本当にやりたいことは自分で事業立ち上げないとできない.他任せではダメだ.他に依存せず,自分のお金と力で生きていき,やりたいことを実現する研究者及び個人事業主を私は目指している.
・夢は反逆や復讐の為でなく,「好きだから」「愉しそうだから」目指すものである.それが反逆や復讐が目的となった瞬間にその夢は諦めた方が良い.というか,「好き」か「愉しい」が原動力でなければその夢は決して叶わないと思う.
〇仕事について(研究者)
・何の為に研究するのか.研究は名誉の為だけではない.社会に還元することは勿論だが,好きだから,愉しいから,やりたいからするのだ.名誉が目的になった瞬間アカデミアは諦めた方が良い.人生の本質は己の幸せであり,それは私にとっては愉しむことである.
・受験戦争によって,勉強=辛い物,優劣をつけるものという先入観が生じてしまっていることが勉強をする上での障壁となる.実際,大学1-3年の私は勉強し過ぎるとプライドが高くなると思っていたことがあった.しかし,勉強は本来愉しいものであり,愉しさを求めて勉強していればプライドは高くならず,まさに「実るほど頭を垂れる稲穂かな」となれる.己自身が勉強を愉しみ,愉しさを伝えられる,そういう人間で在りたいと思う.勉強の愉しさを知らない人間が教えたところで,教えられた子は愉しさを理解できる筈がない.
・他人が〇〇する手助けをしたい,そういう仕事は大切だと思う.しかし,本心はそれだけか?否,私は私自身が主役として愉しみたい.だから,私は研究を享受する者でありながら,研究する者を支える側でもありたい.そういった意味で,大学教員になりたいとも思った.アイデンティティに悩む学生が研究を通じ「自己」に出会い幸せになる手助けをする.特に私は貧困な家庭に生まれたため,学費の面では大いに悩まされ,結果としてFP2級まで取得した.大学教員になり,熱誠があるにも関わらず,お金を理由に進学を諦める学生がアカデミアに残れるように手助けをしたい.
・己は本当に生物と研究が好きなのであろうか?では,なぜ好きなことなのに終業後や休日になぜしてくれないのか?その理由は勉強はエネルギーを使う系であり,同じエネルギーを使う系の仕事と被るからである.しかし,勉強は極めれば極める程,快楽に代わっていき,気が付けば自然と常時するようになるものである.だからまず,その域に達することを目指し努力をする必要がある.決して,好きではないから勉強する気が起きないわけではない.高校一年から10数年間継続しているので,好きであることは間違いない.好きという気持ちはまやかしかもしれない.本当に好きかはわからない.しかし,それは己自身が決めること.なぜならこの世界は無価値で絶対的な理など存在しないから.だから自分にとって都合の良い方,即ち「例えまやかしだと言われても,好きだと思い込み愉しむ」道を選んだ.
〇土蜘蛛の都について
・「土蜘蛛の都」の最終的に目指すところは,生立ちに囚われず,人々が己の幸せのために生きられる世界である.土蜘蛛の都は,私一人の力で築くものではなく,たくさんの人が互いに協力し合い,互いの弱点を補い合うことが総和が完璧になり,人々が人生を愉しめるようになることを目指している.
・土蜘蛛の都を築く上で「伝える」ことは重要.まずは,私自身がその理想を叶える為に全力で努力する.しかし, 自分が生きている期間だけでは叶えられないかもしれない.だからこそ, 次世代に託す.そのために, 自らの考え方を次世代に「伝える」のだ.伝えれば次世代以降が自らの理想を叶えてくれるかもしれない.