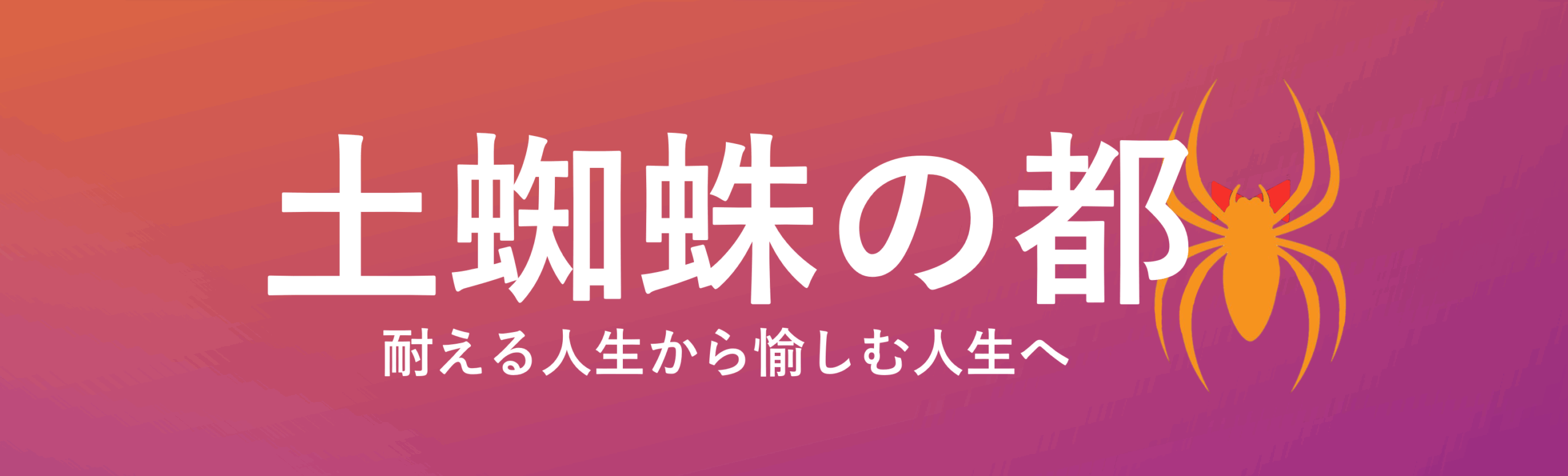クモの所属する鋏角類は,大昔に海に棲んでいた.
現在でも,原始的なグループ(カブトガニ)は海に棲んでいる.
現在クモは陸に棲み,糸や網など他の生物にはない特徴を獲得している.
新しい形質の獲得には,常に新しい環境への適応と関係がある.
本記事では,クモの進化の歴史について紹介する.
①クモの化石
これまでに知られる最古のクモの化石はニューヨーク州の4億年前のデボン紀(4.08-3.6億年前)の地層から見つかったもので,Attercopus fimbriunguisという種名が付く.
化石には糸疣がみられ,糸疣には20個程度の出糸突起がみられるが,其々の形が分化していないことから中疣亜目に類似する.
デボン紀の時点では飛翔昆虫は見つかっておらず,飛翔昆虫の出現は石炭紀以降であることから,本種は中疣亜目と同様に管状住居に棲み,地上歩行性の節足動物を捕食していたと想像される.体節の存在から中疣亜目と同定できる最古の化石は石炭紀のEothele monteceauensis(3.6-2.86億年前),トタテグモ下目最古の化石は三畳紀のもの(2.45-2.1億年前)である.
三畳紀からはクモ下目の化石も見つかっている.もう少し後で,白亜紀(1.4-0.65億年前)の地層からウズグモ科・アシナガグモ科の化石が発見されており,円網の起源はこの頃と考えられる.
②糸の獲得
原始的な鋏角類(カブトガニなど)は海に棲んでいた.
クモが糸を出すようになった起源は,鋏角類が海から陸に適応するためであると考えられる.
クモが陸上に進出したばかりの頃は水辺の高湿度な場所に穴を掘り生活していた.
それが陸上生活に適応する過程で卵を乾燥から守る必要性が現れ,卵塊を包むための粘液が糸の起源になった可能性がある.
③網の進化
クモは地中性から,造網性に進化したと考えられている.
近年の分子系統解析から,円網を張るクモが祖先的で,その一部から立体的な網を張るクモが出現したことが示されている.
立体網の有利な点と言えば,ハチなどの天敵からの防御機能が考えられている.
立体網では,クモは不規則網などの糸で何重にも守られた場所に待機しているため,円網と比べて天敵からの直接攻撃を受けるリスクは少ない.実際,ハチに利用される種は円網を張るクモの方が多い.
ヒメグモ科やサラグモ科は進化的に新しいグループであるにも関わらず種数が多いのは,この天敵からの防御機能に由来するのではないか,と考えられている.
また,円網はゴミの付着・湿度・経時劣化によって粘着力が落ちるために網の定期的な張り替えが必要だが,立体網は必ずしも糸の粘着性に頼っているわけではないために,毎日全ての糸を更新する必要がなく,部分的な補修のみで済むというメリットがある.
このようなメリットから,引っ越しをする率(=網を放棄する率)が立体網性クモでは低めであり,円網は賃貸,立体網は持ち家のようなイメージがある.
④網を張らないクモの出現
網を張らないクモの多くは,あとから現れたと考えられる.
ハエトリグモ,コモリグモ,カニグモ等,網を張らない蜘蛛は約1億年前に多様化した.
これは空中に網を張っていた蜘蛛の一部がそれを捨てる方向に進化した為と考えられる.
なぜなら,この時期は甲虫・蟻等の空を飛ばない昆虫が多様化した時期に一致するから.
また,この時期は被子植物が多様化し,花に寄る昆虫を捕える方向に進化した可能性もある.
原始的な地中性のクモは爪が3本であり,眼の配列は頭胸部の先端に集合している.造網性のクモでは3本の真ん中の爪は網を張る際に利用される.
徘徊性のクモは一般的に2爪(にそう)で,ハエトリグモはその爪の下に末端毛束を持ち,それを使って自由に素早く垂直面を移動できるようになった.
ハエトリグモは眼の配列も大きく変わり,前列眼の2つの前中眼は大きなヘッドライト型の眼になり,良い視力を得ただけでなく色彩も認識できるようになった.
後列眼は四角形の配列になり,横の動きが視野に入るようになる.
一方で,完全な昼行性となり,原始的なクモや多くのクモが持つ夜間見ることに役立つタペータムという視感度を高める膜を失った.
このようにみるとハエトリグモは最も進化したグループの一員と言え,遺伝子を利用した分子系統解析も地中性から造網性,そして徘徊性のクモへと進化したことを裏付けている.