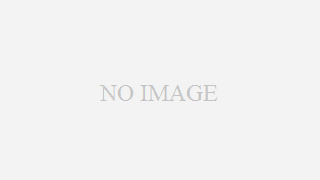 白汐黎
白汐黎 白汐黎の考える研究の愉しさ
こんにちは,企画者の白汐黎です. 現在は研究が大好きな私ですが,嘗ては研究があまり好きではありませんでした. それは,研究室に配属される前の私は研究のことを「学生実験のようななにか」と理解していたからです. 学生実験では,少ない共用試薬を6...
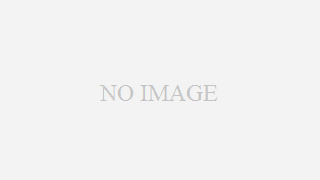 白汐黎
白汐黎  研究
研究  研究
研究  研究
研究  研究
研究 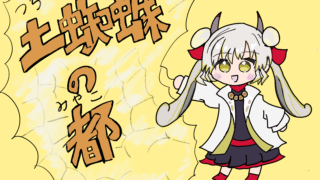 研究
研究  研究
研究  研究
研究  研究
研究  研究
研究