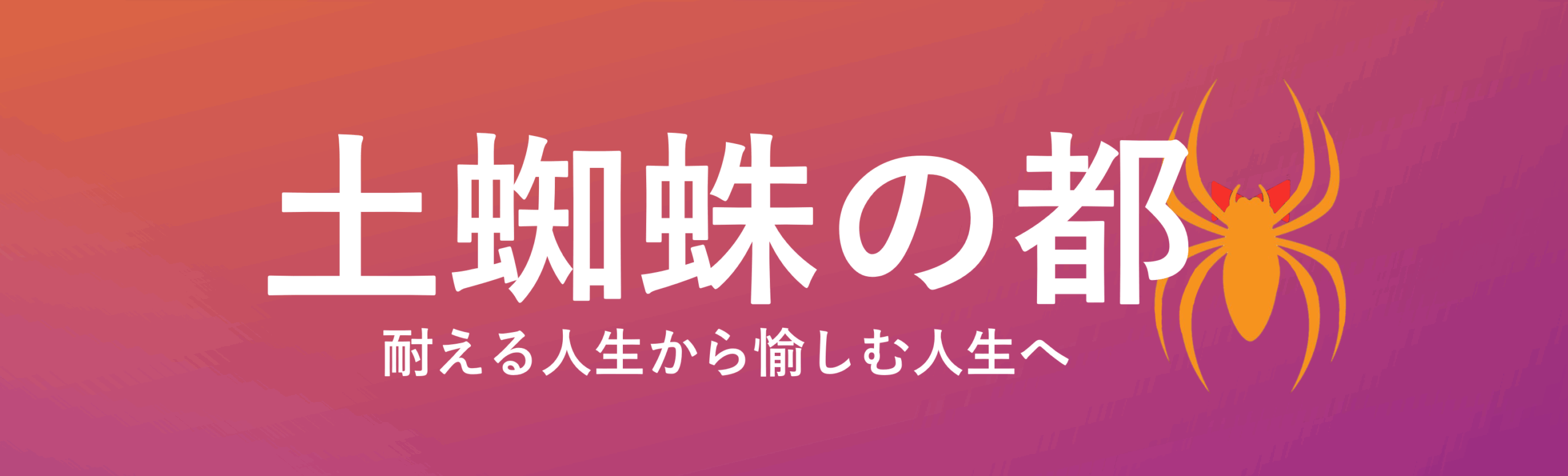昆虫は気管で呼吸をしている.
一方,クモは気管に加えて「肺」で呼吸をしている.
但し,「肺」と言っても脊椎動物の肺とは発生学的に異なる.
クモの「肺」は鰓から進化したものであり,「書肺」と呼ばれている.
①クモの「肺」の進化
クモを含む上位分類群は鋏角亜門と呼ばれ,カブトガニ・サソリ・ダニなどを含んでいる.
特にカブトガニは海産であり,原始的な海産のグループが陸生化したものがクモ綱と考えられる.
クモの腹部に相当する後体部の裏側にカブトガニは腹肢と呼ばれる付属肢が6対ある.
それらの付属肢は遊泳機能だけでなく,鰓の機能を有している.
これは書鰓と呼ばれ,カブトガニの体の外に書鰓が剝き出しになっており,これによって水中の酸素を取り込む.
クモの書肺はカブトガニの書鰓から進化したものであると考えられるが,これは陸に上がる過程で鰓が乾燥することを防ぐために体内に収納されたものと考えられる.
書肺は,多くの肺葉という組織が本のページのように重なり合ってできている.
このことが,「書」肺と呼ばれるようになった所以である.
②クモにおける気管の獲得
書肺に酸素を送るにあたり,書肺気門という孔がある.
原始的なクモ(キムラグモ・ジグモなど)にはこの書肺気門が2対存在するが,ジョロウグモやハエトリグモなどのように派生的なクモでは1対に減少している.
これは進化的なクモでは代わりに「気管」を持つためである.
実際,腹部の裏側をよく見ると気管の呼吸口が開いているのが分かり,解剖をするとその呼吸口から1対の気管が体の中に伸びていることがわかる.
この気管は、後ろの1対の書肺が進化したものである.
気管を持つクモは、持たない原始的なクモと比べると持久力に優れている.
トンボのような昆虫が高い運動量を持つ理由は、全身に気管が発達し、全身に直接迅速に酸素を供給されるからだ.
しかし、気管を持つクモは昆虫と比較して運動量が少ない.
これは,クモの気管は昆虫と比較して毛細血管の発達が悪く,頭胸部の歩脚まで十分に気管系が伸びていないからだ.
それゆえに長時間の高い運動量は実現できないので,「獲物を見つけたら全力で飛び掛かる,獲物が居ない時はのんびりする」「網を張る時だけ頑張る,それ以外の時はのんびり待つ」といった,「必要な時/やる気のある時にだけ頑張る」というスタンスでエネルギーの消耗を抑えている.
頑張っていない時間の方が長く,エネルギーを消耗し辛いので,絶食にはとても強い.
このように,クモの呼吸器には陸棲化や昆虫類(六脚亜門)との関連が観られ,興味深い.