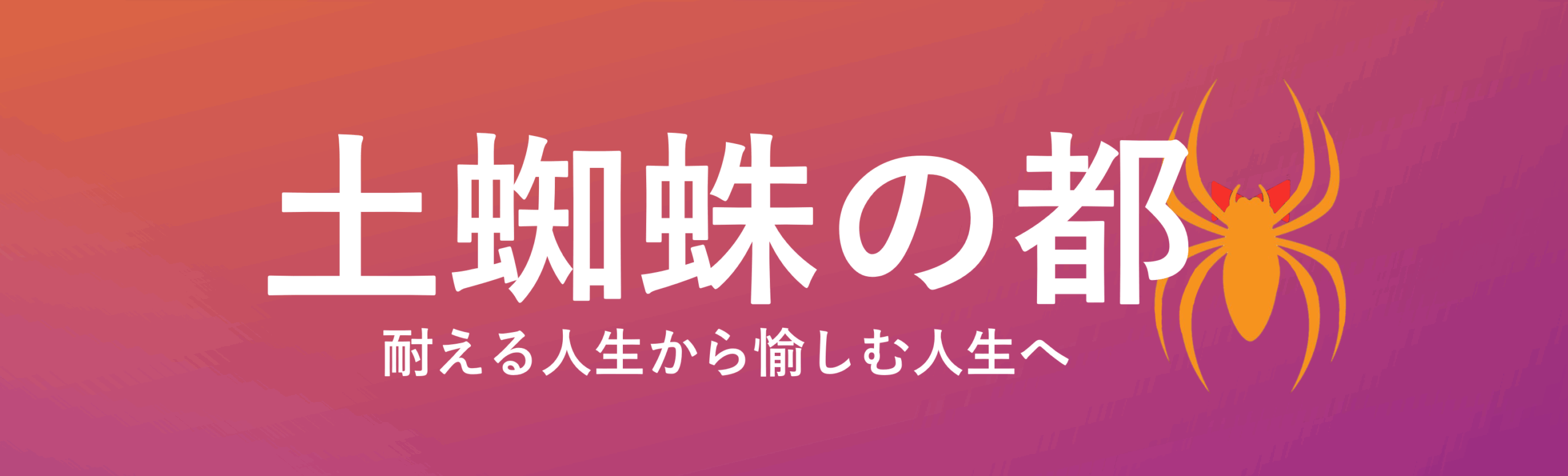クモをキャラクターとして描く際,巨大な牙が描かれることが多い.
巨大な牙は「鋏角」と呼ばれ,クモを含む一連の分類群を特徴づける重要な形質である.
しかし,凶暴に見える牙のイメージとは裏腹に,多くのクモは歯で噛むような「咀嚼」をしない.
寧ろ,化学的な「体外消化」が主な栄養の摂り方なのだ.
①クモの体外消化
クモの口は,上顎(じょうがく)・下顎(かがく)・上唇(じょうしん)・下唇から構成される.
クモの上顎とは鋏角のことであり,頭胸部の第一付属肢が進化したものである.
鋏角の先端には鋭利な牙があり,牙には毒液の射出口がある.
ここから射出される毒液には昆虫などの獲物を麻痺させる役割がある.
ウズグモなどを除いて,殆ど全てのクモは毒を有している.
但し,昆虫と人間では神経伝達物質が異なること,人の皮膚を通過するほど頑丈な鋏角を有する種類が少ないことを理由として,人間に害のある「毒グモ」は日本にゴケグモ類,カバキコマチグモ程度しか存在しない.
下顎は触肢(第二付属肢)の基節が変形したものである.
下顎の内側には唾液の分泌腺があり,消化液を出す.
つまり,人間が口の中から唾液が出て来るのと異なり,クモでは口の外で唾液が出て来る.
この下顎から出て来る消化液によって,クモは体外消化をしているのである.
多くのクモの口には咀嚼をするための歯は生えていないため,クモの食事は咀嚼というよりも下顎から唾液を出して溶かした養分を吸い込むというものになる.
そのため,食事が終わった後の獲物はカラカラの肉団子と化す.
口には食道を介して胃が繋がっているが,胃は消化を行わず,体外消化した獲物を吸い込むためのポンプのような役割を果たす(そのため,吸胃と呼ばれる).
②クモの消化器官
クモの場合,口から肛門までを腸と呼び,腸は前腸(頭胸部に位置する口から胃まで),中腸(頭胸部から腹部にかけて位置する,腸の大部分を占める),後腸(肛門付近だけ)から構成される.
中腸には盲嚢(袋状の分枝)が多数あり,大食いをしても消化吸収がされて,お腹を壊さないようにできている.
中腸の肛門に近い部分には排出嚢があり,便を溜めておくことができる(人間で言う大腸).
中腸と後腸の境目にはマルピーギ管が開口しており,腎臓的な役割を果たす.
肛門は総排出孔なので,マルピーギ管由来のグアニンを含む白い液体に黒い糞が混じった状態で排出される.
クモは他に基節腺という排出器官を頭胸部に持つ.
こちらも腎臓のような役割であり,窒素化合物(尿)を体外に出す働きをする.
原始的なクモの方が基節腺が発達し,糸腺(糸を生成する器官)の発達具合と反比例するとされており,このことから糸の生成に使わなかった窒素を基節腺やマルピーギ管で排出する,ということかもしれない.
このように考えると,糸腺も一種の排出器官とみなせる.