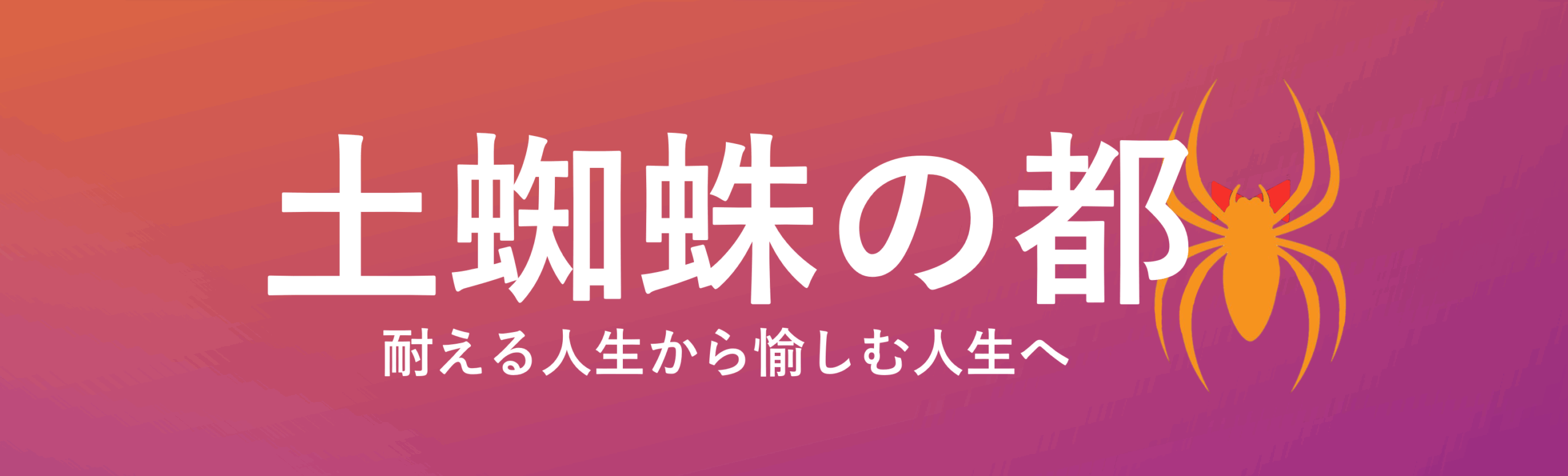我々人類を含む哺乳類は紫外線を視認する能力を欠いている.
これは,恐竜が全盛期の時代,哺乳類は隠れるように夜に活動をしていたため,紫外線を視認する必要がなくなったためであると考えられている.
一方,クモや昆虫,鳥などの哺乳類以外の動物は紫外線を視認することができる.
クモは昆虫を相手に網を張るため,紫外線を活用した餌の捕まえ方を進化させてきた.
本記事では,クモがいかに紫外線を含めた光と付き合ってきたかについて述べる.
①夜行性のクモと昼行性のクモ
コガネグモ科のクモは,夜に網を張るタイプ(オニグモ類)と昼に網を張るタイプ(コガネグモなど)に明瞭に分けられる.
円網は劣化し易いため,一日中網を張り続けることは非効率であり,昼か夜の片方に特化している.
系統的には夜行性のクモが先に出現して,その後に昼行性のクモが派生したと考えられる.
昼行性に進化した理由は単純に昼間の方が利用可能な餌の種類が多いことだが,昼間は天敵や気温の問題があるために,トレードオフであると考えられる.
そのため,現在でも夜行性のクモの方が種数が多い.
また,昼行性と夜行性のクモの間で円網の糸の特性が異なっている.
夜行性のクモの網は紫外線の反射が強い.
一方,明るい環境に棲む粘球性円網を張るコガネグモなどでは,紫外線領域の反射がとても弱い.これは明るい環境(日中)で紫外線反射が強いと,昆虫が容易に網を認識して避けてしまい,餌がかからないためであると考えられる.
逆に昼行性のクモでは網全体の紫外線反射が弱いため,部分的に紫外線を強く反射する部分を作ることによって,獲物を誘き寄せることもしている.
②円網にある隠れ帯(捕帯)
上記で説明した部分的に紫外線を強く反射する部分は隠れ帯(捕帯)と呼ばれる.
隠れ帯は白色でよく紫外線を反射するために,このことが天敵回避,鳥による網の破壊防止,獲物となる昆虫の誘因などに役に立つという説がある.
天敵回避については,例えばコケオニグモでは地衣類(紫外線反射が強い)の生える場所に,隠れ帯付きの円網を張ることで,紫外線色を同化させて擬態をするという.
鳥による網の破壊防止については,隠れ帯が紫外線をよく反射して鳥にとって目立つために,鳥が網を壊さなくなるという説がある.
獲物となる昆虫の誘因については,昆虫が紫外線に誘引される性質を利用して,紫外線を反射する隠れ帯で昆虫を誘引しているという.
一方,隠れ帯の存在は目立つがゆえにハチなどの天敵に見つかりやすくなるデメリットもある.
例えば,コガネグモなどでは隠れ帯の形や本数を変えたりすることがあるが,これはメリットとデメリットのバランスをとるための調整と考えられる.
コガネグモの隠れ帯にはX字状と直線状のものがあり,X字は餌を誘き寄せるため,直線はクモのいる場所を分かりにくくして捕食者から身を守るためである,という説がある.
面白いのが,虫は眼が悪いためにX字の隠れ帯を花と間違えて近づくという説である.
昼行性のクモの網は全体的に紫外線を殆ど反射しないが,隠れ帯は強く反射するため,紫外線写真では花の写真と隠れ帯のパターンは確かに似ている.
また,直線状の隠れ帯を持つナガコガネグモの後ろから紫外線写真を撮ると,姿が見えなくなる.